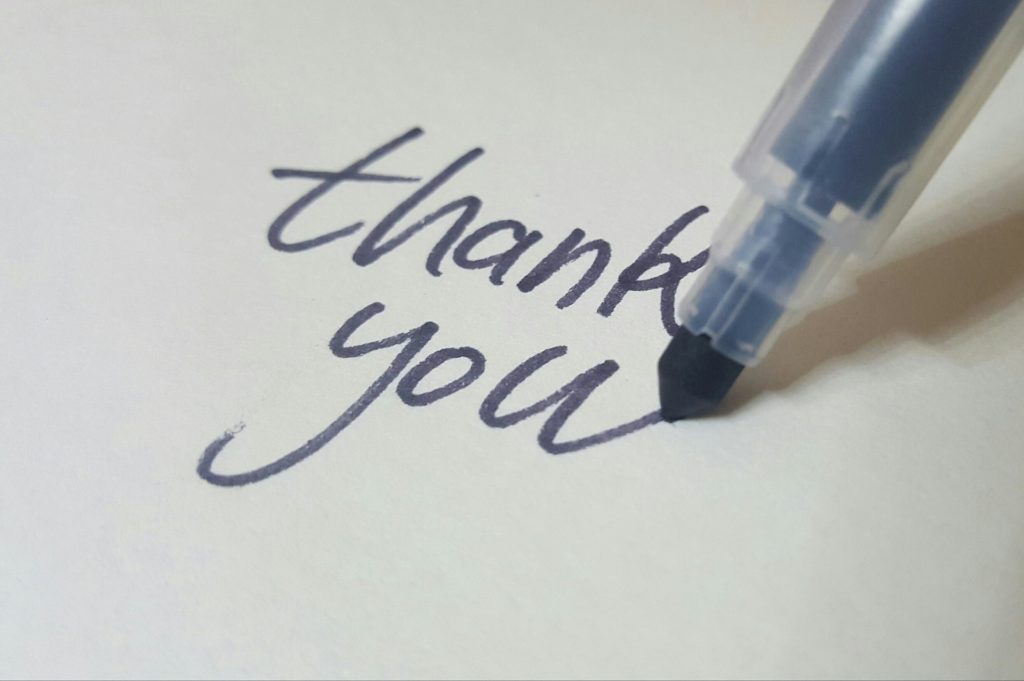
本記事では、小林正観さんの著書
を読んだ要約・感想をまとめています。
「ありがとうの魔法」では小林正観さんが40年の研究で得た
神様が味方になる68の習慣
について書かれています。
日々の生活で起こる
- 人間関係
- 仕事
- お金
- 病気
- 子ども
- 運
- イライラ
- 男女
の悩みがすーっと消えていく魔法のような本です。
小林正観さん曰く、「ありがとう」を言うだけで「神様」を味方につけることができて自然と人生が好転していくんだって。
さらには、がんばってがんばって必死に努力するよりも感謝をして(ありがとうを言って)神様に味方になってもらう方が人生お得らしい。
そして、ただひたすらに今在ることを喜び、ありがとうを口にして感謝していると自然と「ありがとう」が返ってくる。
そして幸せに生きることができる。
長年生きているといろんな悩ましい出来事が起きるじゃないですか。
そのたびに悩んだりしますが、良いことも悪いこともその出来事そのものに感謝すれば神様が味方になって助けてくれる。
そんな魔法のつまった本です。
小林正観さんの著書、「ありがとうの魔法」を読んだ感想をまとめました。
ありがとうの魔法を読んだ要約
小林正観さんの「ありがとうの魔法」は過去に出版された”一番いいお話”を集めた「ベスト・メッセージ集」の第3弾です。
第1弾は2015年2月13日に発売された「ありがとうの神様」
第2段は2016年11月25日に発売された「ありがとうの奇跡」
です。
第3弾のありがとうの魔法では神様が味方になる68の習慣について書かれています。
ありがとうの魔法に書かれている68の習慣はどれも特別なことではなく普段の生活の中で実践できます。
考え方を少し変えたりやり方を少し変えるだけで人生が好転していきます。
少しネタバレになっちゃいますが、あなたはコップの水がほとんど入っていない時に、
「少しだけ残してくださっていてありがたい」
と思えますか?
「こんなに少ないんじゃ意味ねぇ!」
とか
「もっと水をくれ!」
とか思ったりしませんか?
仮にコップに水が半分入っていたとしても、7割入っていたとしても「満ち足りていない=満杯ではない」と言って満足できない人もいます。
なかには100%入っていたとしても「100%しかない」と不満を感じる人もいると思います。
すでに100%存在していて、それ以上はないはずなのに満足できない。
そうではなく、全てのことに対して「ありがたい」と思えるかどうかなんです。
コップにほとんど水が入っていないときに
「誰かが少しだけ残してくれてありがたい」
と思えると心が穏やかになれます。
今在ることに目を向けると現時点で十分幸せであることを感じることができます。
物事の大小はあるけれども「在ること」に目を向ければ、自分の周りにはたくさんのことで満ち足りていることに気づきます。
小さな在ることにも感謝することができようになるとたくさんの幸せを感じることができるのです。
ありがとうの魔法を読んだ感想
ありがとうの魔法を読んで思ったこと。
自分が気づいていないだけで周りには幸せなことがたくさん満ちあふれているということ。
- 子どもが毎日元気に過ごしている
- 手に職があり普通に働いている
- 毎月給料がもらえる
ことの大小はあれどあることには間違いない。
子どもが少しくらい勉強しなくたっていいじゃない。
やれる仕事があるならいいじゃない。
給料が平均よりも少なくてもいいじゃない。
子どもが楽しく元気に過ごしてるなら、それはすごく幸せなこと。
仕事があるなら、それだけで幸せなこと
給料がもらえてるなら、それだけで幸せなこと。
「在る」に目を向けると、それだけで在ることのありがたさに気が付きます。
わたしたちはもうすでに十分幸せなんです。
なので、まわりの在ることに感謝し(受け入れて)、心から「ありがとう」を言えばいいんだと思います。
そして、その先に人に喜ばれる存在になること。
自分のためではなく人のために。
いかに人に喜んでもらえるかを考えると、商売や人間関係は自然と良くなっていくそうです。
まとめ
小林正観さんの著書「ありがとうの魔法」を読んだ感想・要約をまとめました。
幸せの本質は
「今足りないものを探して手に入れること」
ではなくて、
「自分がすでにいただいているものに感謝し、自分が恵まれていることに気づき、嬉しい、楽しい、幸せ・・・と生きていること」
だそうです。
不平不満や泣き言を言わず、何が起ころうともすべてのことに「ありがとう」と感謝する。
そうすることで神様が味方をしてくれるので人生が好転していきます。
人は一人で生きていると「ヒト」ですが、喜ばれるように生きていくと人と人の間で生きる「人間」になります。
人間らしく生きるために、ありがとうと感謝し喜ばれる存在になること。
これが幸せに生きる近道だと思いました。










